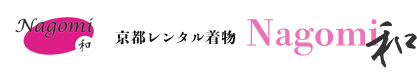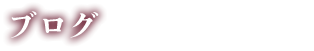- 伝統と作法~二礼二拍手一礼~2019.2.9
-
みなさま
こんにちは
こんばんは
おはようございます!
伏見稲荷大社の側にある京都レンタル着物Nagomiでございます。
今日は気温が低く寒いですね。
関東は大雪の予想みたいなので
お住まいの方は充分にお気を付け下さい。
本日は
お参りといえばコレ!!
詣でに参った人が欠かすことがないと
言っても過言ではない
参拝です。
参拝の作法といえばよく耳にするのが
二礼二拍手一礼(二拝二拍手一拝)
神前で行う行為であり
場所によっては二礼四拍手一礼など
異なることがあります。
出雲大社、宇佐神宮などは二礼四拍手一礼が
正しい作法とされています。
今回は一般的に多く用いられてる
二礼二拍手一礼の手順を説明致します。
①
神前に立ち、姿勢正します。
②
お賽銭箱にお賽銭を入れます。
この時、お賽銭は投げ入れるのではなく
そっと入れることが良いとされています。
③
鈴を鳴らします。
④
2回拝みます。
この時、角度は90度が正し姿勢です。
⑤
胸の前で手を合わせます。
この時に右手を下に少しずらします。
手をずらす理由は
左手が神様、右手が人であり
その後、合わさることにより
神様と人が一体となって、神様の力を
体得できるという考え方です。
⑥
2拍手をします。
拍手後は指先を合わせください。
*理由は前述
⑦
そして最後に1礼してください。
以上が二礼二拍手一礼の手順です。
またお賽銭の金額ですが、特に決まりはありません。
なので5円(ご縁がある)、50円(五重に縁がある)など
縁起のいい金額が好まれるようです。
それと金額が多いから
神様が張り切って願いを叶える
なんてことはありません。
お賽銭とは、白い袋にお米を入れて
お供えしていた名残りであり
大事なものを捧げることで私欲がないことを
伝える意味があります。
なのでお賽銭を入れないで
参拝してはダメですよ!
本日はここまで
次回は二礼二拍手一礼(続)
Nagomiでお着物を着て参拝なんていかがですか?
可愛いお着物を着て参拝すると
願いが叶う
可能性もアップ…..かもしれません。

ブログ
- 可愛い😍刺繍えり2019.2.8
-

 伏見稲荷側にあります、京都レンタル着物Nagomiです。
伏見稲荷側にあります、京都レンタル着物Nagomiです。今日は、可愛い刺繍えりをご紹介させて頂きます🌟💐🌟
お着物を着ると、写真のようにお襦袢(じゅばん)の襟が、チラリと見えます。
Nagomiでは、お着物のプランにかかわらず、すべてのお着物に可愛い刺繍の入った色襟をご用意しております❣️
お着物とお襟のコーディネートも楽しんで下さいね🌺
- 伝統と作法~名称編~2019.2.7
-
みなさま
こんにちは
こんばんは
おはようございます!
伏見稲荷大社の側にある京都レンタル着物Nagomiでございます。
先日行った店がテレビで紹介されていて
「この前行ったとこー♪♪」と
テンションが上がった今日この頃です。
なんか嬉しいですよね。
今日は拝殿の前でのお話しです。
ここでよく目にするものが
鈴
鈴の付いた紐
がありますよね。
この鈴と紐には正式名称があります。
神社で見かける鈴を『本坪鈴(ほんつぼすず)』といいます。
神社の鈴でも間違いではありません。
またお寺などの鈴は『鰐口(わにぐち)』という
名称があります。
この2つには形はもちろんのこと
用途にも明確な違いがあり
お寺の『鰐口』は仏様にご挨拶や
お参りに来たことを知らせるためにあります。
神社の『本坪鈴』は魔除けの意味があり
鈴除けとも呼ばれることがあるそうです。
また同時に神霊を呼び起こす意味も
あるそうです。
そして鈴の付いた紐ですが
こちらを『鈴緒(すずお)』といいます。
『緒』とはつなぐという意味があり
なので鈴緒には
神々の世界と現世をつなぐものという
考え方があるようです。
へその緒の緒も同じく母と子を
つないでるものですよね。
ちなみに『玉緒』は日本を代表する
名女優です。
球体をつなぐものではありません(笑)
本日はここまで
次回 二礼二拍手一礼
Nagomiでお着物を着て鈴緒を振って
お参りされてみてはいかがですか?
お客様のご来店お待ちしております。

- 伝統と作法~鳥居~2019.2.6
-
みなさま
こんにちは
こんばんは
おはようございます!
伏見稲荷大社の側にある京都レンタル着物Nagomiでございます。
昨日の穏やかな天気に比べて
本日は朝から雨ですね
午後から晴れるみたいなので
待ち遠しいです。
前回の続きです。
これから拝殿に向かいます。
この時、参道の中央は神様の通り道ですので
両端を歩くことが
作法とされております。
また鳥居の前では一礼をして
左足から入ることも
参拝の作法とされております。
ただ伏見稲荷大社の千本鳥居ですると
腰を痛めそうですね。
なので最初の鳥居で一礼して
以降は「詣でに参りました」という
気持ちを込めて進めば大丈夫かと思います。
ちなみ千本鳥居で想像すると
一礼→進む→一礼→進む
↓
進む←一礼←進む←一礼
鳩の動きが思い浮かびました(笑)
本日はここまで
次回、参拝…..までにあと少し
まだなんかいっっ!!!
Nagomiでお着物を着て千本鳥居を歩かれてみてはいかがですか?
雨の日もお客様のご来店お待ちしております。

- 伏見稲荷は交通が便利2019.2.5
-

伏見稲荷側にあります、京都レンタル着物Nagomi です。
今日は穏やかなお天気ですね☺️
お着物でお出かけされてみてはいかがでしょうか?
伏見稲荷は、JR「稲荷」駅と、京阪「伏見稲荷」駅があり、交通がとても便利です。
JRで京都駅まで5分程で、京阪で祇園四条まで8分ぐらいで行けます🚃🚃
お着物を着られて、伏見稲荷、祇園界隈、八坂神社、清水寺など、京都観光されるのもお勧めです⛩
Nagomi に是非ご来店下さいませ。
- 伝統と作法 ~参拝前に~2019.2.4
-
みなさま
こんにちは
こんばんは
おはようございます!
伏見稲荷大社の側にあるレンタル着物Nagomiです。
前回は手水舎で身を清めたので
さぁこれから参拝…..の前に
門の下などで目にすることのある敷居ですが
この敷居を踏んではイケない
ということはみなさまもご存知だと思います。
でもなぜ踏んでは駄目なのかご存知でしょうか?
ちなみに私は知りません!!!(笑)
なので調べました!(笑)
諸説ありますので
神様に因んだ説を紹介します。
『しきい』とは現代では敷居と
書かれていることが一般的ですが
以前はこの『鴫』という字を使い
鴫居(しきゐ)が一般的でした。
そして鴫居の上の部分を鴨居といいます。
『鴫(しぎ)』も『鴨(かも)』もどちらも水鳥です。
下から鴫が
上から鴨が
その建造物を火災から
守っているという考えかたです。
イメージではこんな感じでしょうか。


元々の日本家屋は木造建築が主流で
火災に弱い作りでもありました。
そのため、防火の神様を
『鴫』と『鴨』の水鳥にたとえ
家を火災から守って下さっていたのです。
なので神様のいる敷居を踏むと
その敷居から神様がお離れになる
という思いから「敷居を踏んではいけない」と
言い伝えられてきたそうです。
ちなみに鴨ですが
当店の近くでたまに泳いでいるとこを
見れることがあります。
鴫はおりません!(笑)
本日はここまで
次回、今度こそ参拝…できるかな
Nagomiでお着物を着て敷居を踏まずに
散策はいかがですか?
華やかなお着物をご用意して
お客様のご来店お待ちしております。
- 伝統と作法2019.2.3
-
みなさま
こんにちは
こんばんは
おはようございます!
伏見稲荷大社の側にあるレンタル着物Nagomiです。
日本は昔からの伝統や作法、ルールが
どこに行ってもありますよね
食事や工芸品など、伝統や作法に関わる機会が
多いと思います。
もちろん大社や神社にも作法がたくさん。。。
その中の1つ『手水舎』を紹介します。
手水舎…..読み方ですが『ちょうずや』『てみずしゃ』
現代では『てみずしゃ』と読むことが一般的だそうです。
そもそも手水舎ってなんだ?
 手水舎とは
手水舎とは柄杓が置かれており
水盤から手水をすくい
参拝前に
身を清める場所です。
この手水舎にも作法が存在するのです
 1、手水舎に向かい
1、手水舎に向かい軽く会釈をして水盤の前に立つ
2、右手で柄杓を持ち左手を清める
3、柄杓を左手に持ち替え右手を清める
4、柄杓は左手のまま右手に手水を用いて
口を漱ぎます
(柄杓から直接口を漱いではいけません)
5、右手に柄杓を持ち、再び左手を清めます。
6、柄杓を立てて
残りの手水で柄杓を清めたら終わりです。
工程がおーおーい!!!
覚えられるかっっっ!!!って方!
安心してください。
手水舎の多くには図のような説明が書いてあることが多いです。
本日はここまで
次回は本殿に参拝だぁ♪♪♪
Nagomiでお着物を着て伏見稲荷大社へ参拝はいかがですか?
もちろん18:00まではどこへ散策に行かれても構いません
楽しい思い出を作ってお戻りくださいませ。
お客様のご来店お待ちしております。
- 伏見稲荷初午2019.2.2
-
 伏見稲荷の側にありますレンタル着物Nagomiです。
伏見稲荷の側にありますレンタル着物Nagomiです。ホームページをリニューアル致しました。
可愛いお着物をたくさんご用意して
ご来店お待ちしております。
本日は伏見稲荷大社の初午でした。
- ホームページをリニューアルいたしました。2019.1.29
-
この度、当ホームページをリニューアルいたしました。
今後とも、京都レンタル着物Nagomiをよろしくお願いいたします。